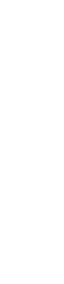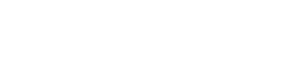PROGRAM 研修プログラム
研修プログラム概要
研修計画(基本プログラム)
※1年次の当初1週間はオリエンテーションを実施します
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1年次 | 内科 (24週) |
救急 (8週) |
外科 (4週) |
小児 (4週) |
産婦 (4週) |
精神 (4週) |
||||||
| 救急 (週1回の当直) ➜ | ||||||||||||
| 2年次 | 一般 外来 (4週) |
地域 医療 (4週) |
選択科目(概ね40週) | |||||||||
| 救急(週1回の当直) ➜ ※2年間通年で当直を行い、救急部門4週分をカウント | ||||||||||||
1.全体研修期間
研修期間は原則2年間とする。
2.研修を行う分野とその研修期間
① 必修分野(※必修分野における週数は最低限の期間であり、目標達成状況により適宜追加する)
内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神神経科及び地域医療を必修分野とする。
一般外来の研修も含める。
■内科(24週以上)
糖尿病・内分泌内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科より選択する。
■救急部門(12週以上)※基本実施項目
救急診療科を中心に頻度の高い症候と疾患、緊急性の高い病態に対する初期救急対応能力の習得を目指す。
救急診療科と麻酔科で8週、救急外来宿日直で4週の研修を行う。
松江赤十字病院救命救急科での研修も可能とする。
■外科(4週以上)
消化器外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科より選択する。
■小児科(4週以上)
■産婦人科(4週以上)
■精神神経科(4週以上)
■地域医療(4週以上)
原則として、2年次に地域医療研修を行う。一般外来研修と在宅医療での研修を含める。
■一般外来研修(4週以上)
当院総合診療科と地域医療または研修協力施設の開業医において研修を行う。
研修期間に不足が生じた場合は選択科目(総合診療科、小児科)で補うものとする。
② 必修分野以外(選択科目)
研修医の希望を基本に到達状況を踏まえて選択科目を決定する。(当院で選択可能な診療科については研修プログラムを参照)
協力病院、協力施設での研修可。
(※ただし、1年次が終了した時点で到達目標に未到達がある場合には到達目標達成に必要な必修分野での研修を追加して行うこととする)
3.その他の研修
2年間の研修において、院内感染や性感染症等を含む感染対策、予防接種等を含む予防医療、虐待への対応、社会復帰支援、
緩和ケア、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)、臨床病理検討会(CPC)等、基本的な診療において必要な分野・領域に関する
研修を必修とする
4.医師育成のための教育体制
- 救急外来で出会う各科に特有な救急疾患など個別のテーマについて、担当指導医によるレクチャーを実施する
- 臨床研修に必要な基本的手技について、担当指導医によるレクチャーを実施する
- 院内講師による研究会や院外専門家による講演会、研究会を開催する
- 救急外来などで経験した症例をもとに研修医カンファレンスを毎週金曜日の早朝に行う
- 救命救急に必要な知識・技術の取得のため、BLS及びACLSの講習会を受講する
- 感染症診療の基礎となる細菌の鑑別知識と手技を習得するためのレクチャーを実施する
5.研修医用レクチャー・カンファレンス実施内容
1.感染症基礎研修
2.エコー実技研修
3.病理症例検討会
4.研修医カンファレンス
5.各診療科指導医による研修医のためのレクチャー
6.その他教育に関する行事
- 基本的臨床能力評価試験(研修医全員参加)
- 松江市立病院研究会
- 院外の研究会・学会への参加
- ローテーション各科の症例検討会、抄読会、カンファレンスなど
- 緩和ケア研修会
- 病院全職員を対象とした研修会、各種委員会の勉強会
※ACP、キャンサーボード、ゲノムエキスパートパネルに積極的に参加する
研修協力病院
研修協力施設
雲南市立病院、町立奥出雲病院、隠岐広域連合立隠岐病院、隠岐広域連合立隠岐島前病院、社会医療法人仁寿会加藤病院、
医療法人財団公仁会鹿島病院、飯南町立飯南病院、知床らうす国民健康保険診療所、松江市・島根県共同設置松江保健所、
大國内科クリニック、たにむら内科クリニック、いちえ内科クリニック